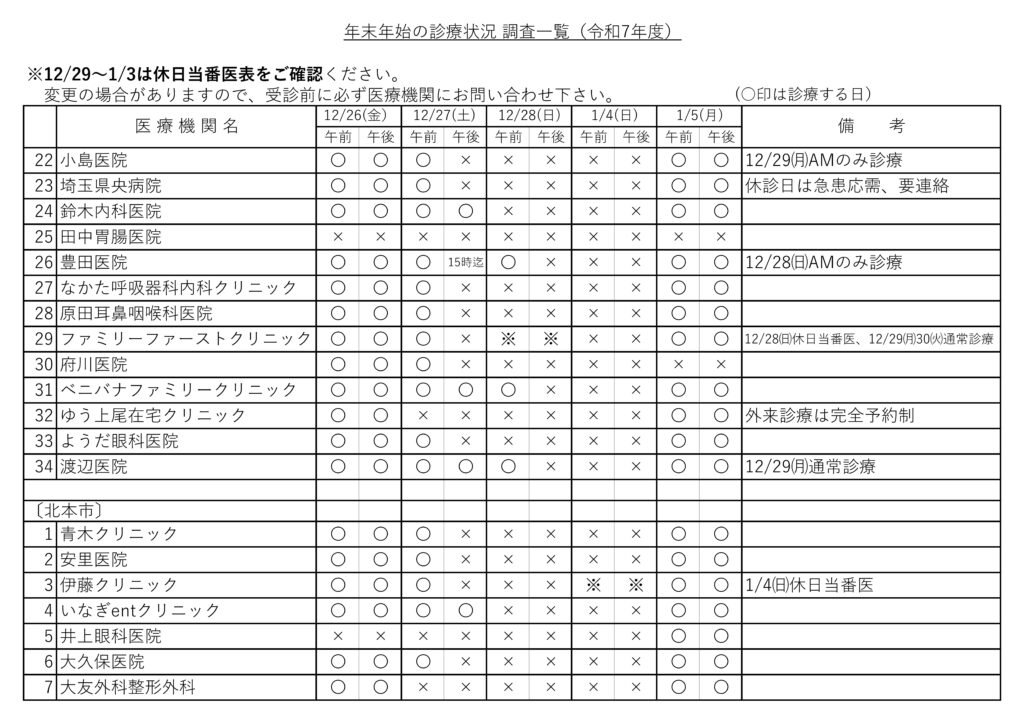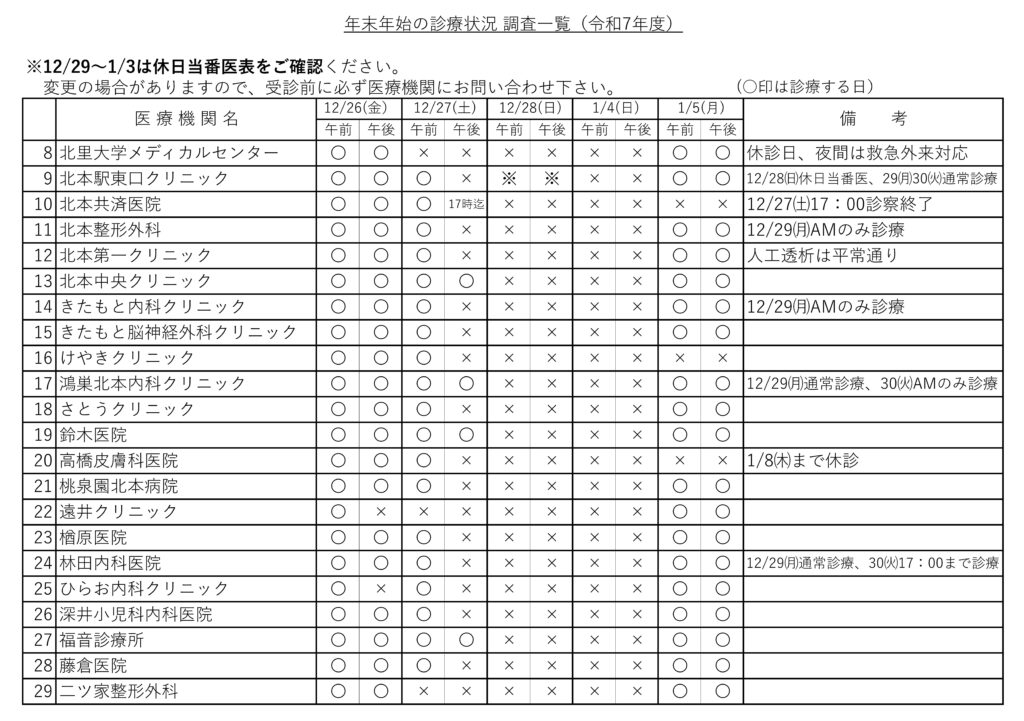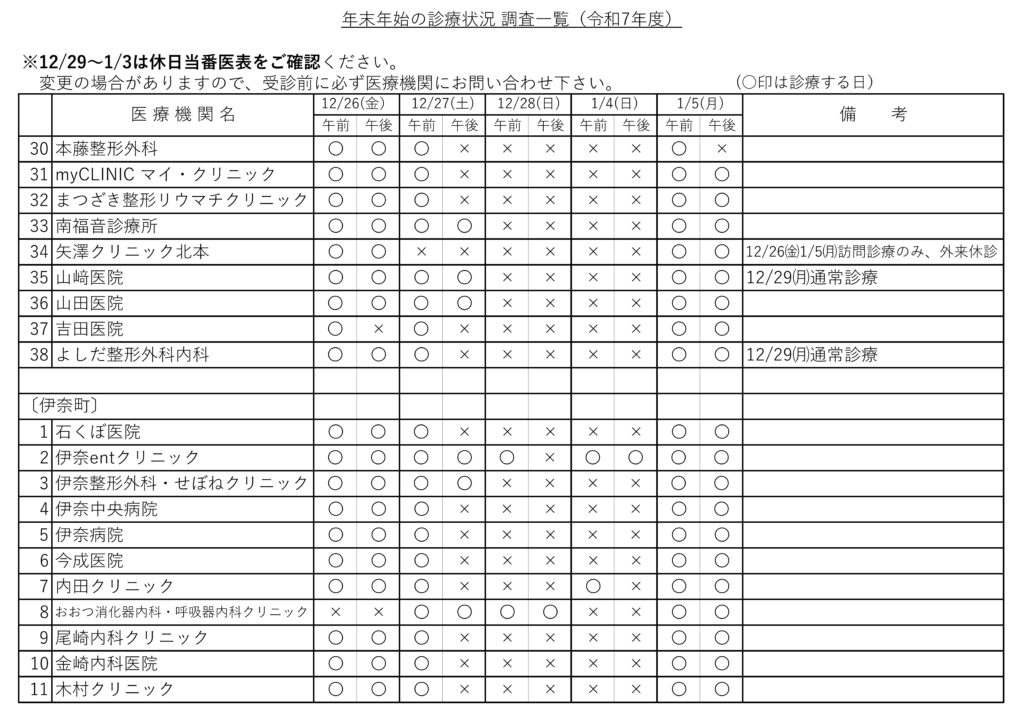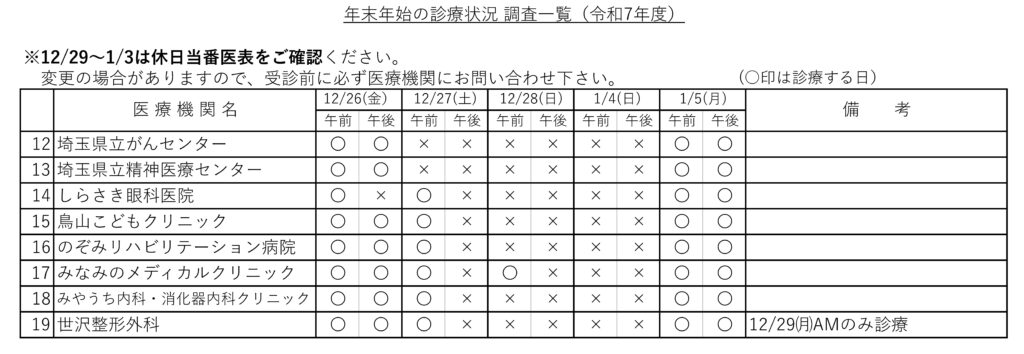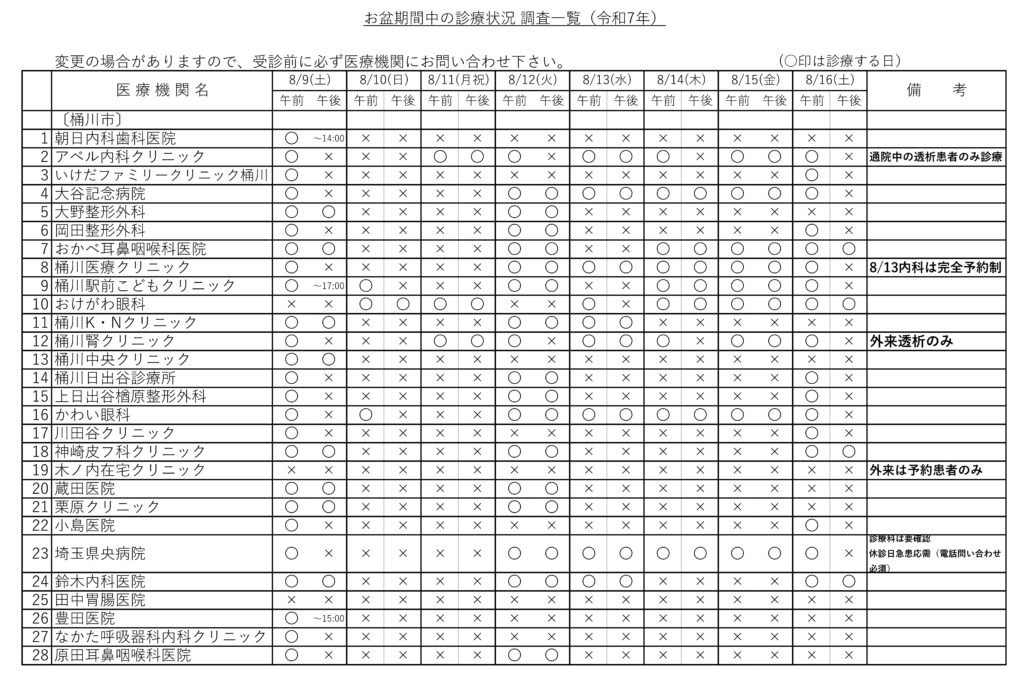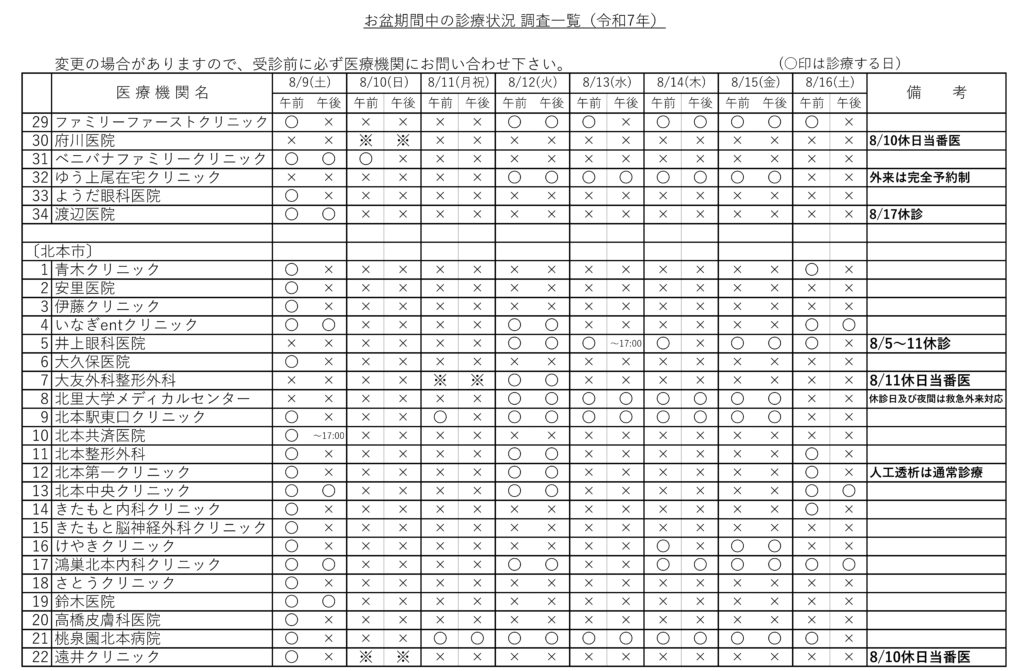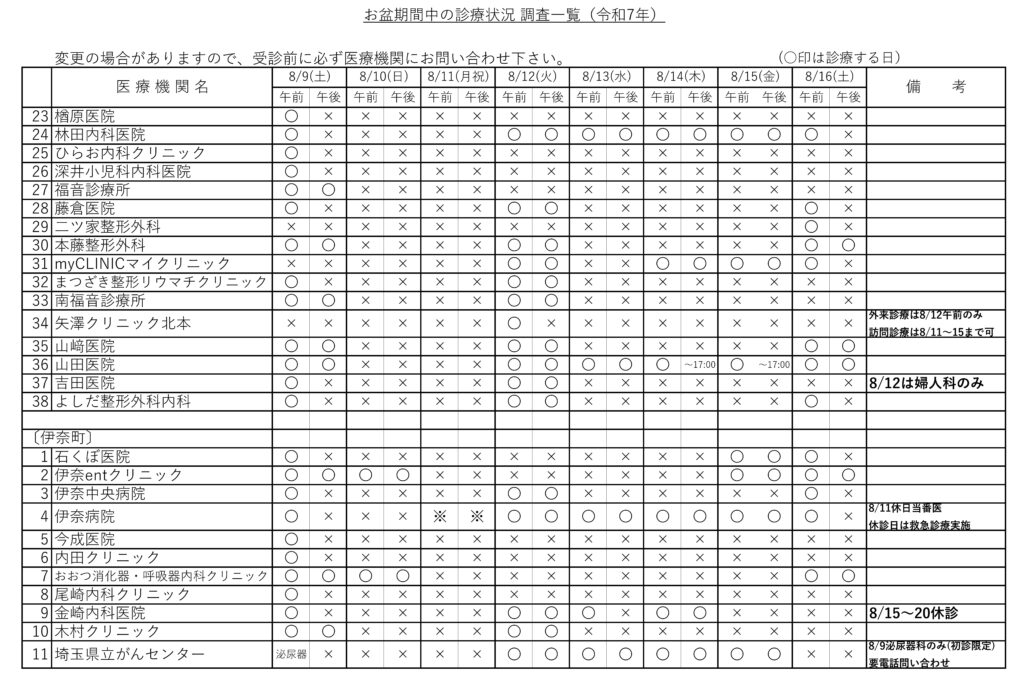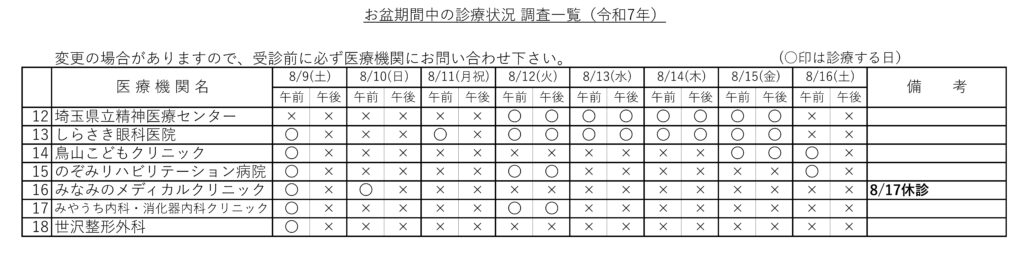健康一口メモ12月号 『ヒートショック』を掲載いたしました
お風呂からなかなか出て来ないなと思って、見に行ったら家族が倒れていた。湯船で溺れていた。なんていう話を聞いたことはありませんか。
あまりに急激な温度変化がおこると、血圧が急に上下して、身体がダメージを受けることがあります。これがヒートショックです。
暖かい所から寒い所への移動でも、その逆でもヒートショックは起こります。だから冬の入浴には、注意が必要なのです。
厚着をして、暖かい部屋にいた人が、寒い脱衣所に行き、服を脱ぐと、体が急に冷えます。すると自律神経が働いて、血管が縮こまって、血圧が上がります。しかし、浴槽につかると、今度は熱いお湯で急に体が暖まり、逆に血管がゆるんで広がり、血圧が下がります。65歳以上の高齢者や、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの持病がある人は血圧を正常に保つ機能が低下していることがあり、ヒートショックのリスクが高いと言われています。軽症では、めまいや立ちくらみがみられ、重症では、失神して意識を失ったり、脳卒中や心臓発作を起こすこともあります。
予防策は以下の通りです。
① 温度差を少なくする:
脱衣所を暖める。床にマットを敷く。浴室を暖めておくために、お湯をはる時にシャワーを使ったり、浴槽のふたを開けておいたりする。シャワーやかけ湯で体を暖めてから入浴する。お湯は38-40度位であまり熱くしない。
② タイミングに注意:
比較的寒くない昼に入浴する。浴室が冷えている一番風呂を避ける。食後1時間や飲酒後は血圧が下がりやすいので避ける。睡眠薬など眠くなる薬を飲んだ後は避ける。長湯をせず、10分くらいに。入浴前に飲水を。
③ 万が一に備える:
意識を失っても溺れないように、お湯の量を少なめにする。胸までつかる位に。(発見時はまず、栓を抜き、お湯を捨てる。)入浴前は家族に声をかける。
国の推計では、入浴中の事故で亡くなる人は年間19,000人にもなるとされます。十分な準備をして、入浴してください。